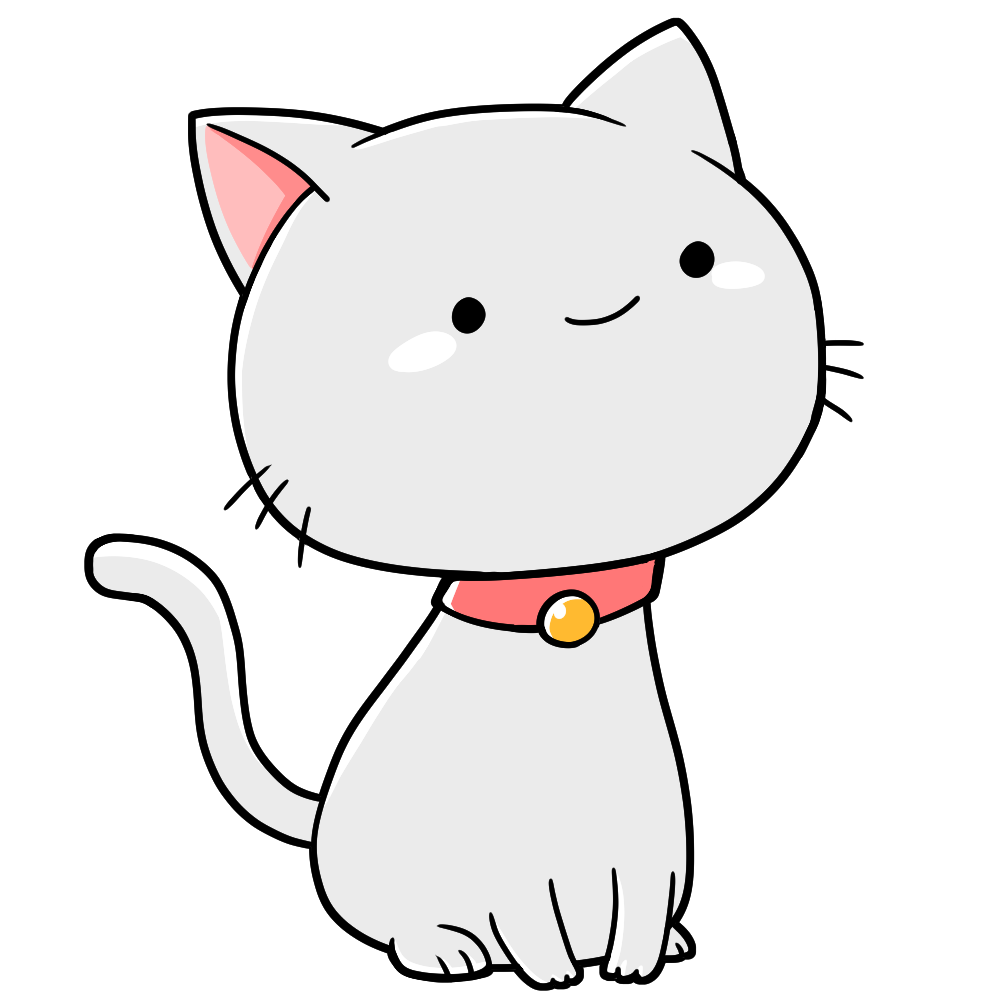猫になめられた時ザラザラとした感触とともに少し痛みを感じることがありませんか?
あのザラザラにはどんな役割がついているのでしょうか?
今回はそんな猫の舌について詳しく解説や紹介していきたいと思います!!!
もくじ
猫の舌がザラザラしている理由

猫の舌のザラザラ正体は【糸状乳頭(しじょうにゅうとう)】と言われるものです。
舌全体に無数に生えています。これが見る限りトゲのように生えていますね。
これが猫の舌でなめられるとザラザラとして痛い原因です。
子猫の時はこの糸状乳頭(しじょうにゅうとう)はありませんが、お母さんの母乳から離乳すると少しづつ糸状乳頭(しじょうにゅうとう)が現れ始めます。
ザラザラの舌にはどんな役割があるのか?

あのザラザラにはどんな役割があるのでしょうか?
調べてみました。
そしたら2つの役割を見つけましたのでそれぞれ紹介していきます。
骨から肉をそぎおとすため
野生の時は獲物を捕獲し食べていました。
現在とは違い、いつでもエサが食べれるというわけではありません。
なので余すことなく骨についた肉まで食べていました。
その骨についた肉をそぎ落とすためにそのザラザラの舌を使っていたのです。
これは現代に必要なのか?
と思う方もいると思いますが、実は現代にも役立っているそうですよ!
エサの容器についたものを残さずに最後まで食べることに役立っています。
ほかにはどう役立っているのでしょうか?
毛づくろい
そもそも毛づくろいとは何なのでしょうか?
それにいくつかの理由があります。
- 体温調節
- ほこりや抜け毛を除去
- 精神を安定させる
- 愛情表現
1つ目の体温調節です。
猫などの動物は汗をかくものが少ないです。
なので猫は足裏の肉球に汗腺があります。
そこの汗腺からしか猫は発汗することができません。
なので、体温が上がったら身体中を舌で舐めて唾液で蒸発させて、体温を空気中に逃がせているのです。
2つ目のほこりや抜け毛を除去です。
ほこりや抜け毛を舌をブラシを代わりにして体をきれいにしています。
このおかげであまりシャンプーやお風呂にはいったりしなくてもキレイを保てているのでしょうね!
この行為には、ブラッシング効果や皮膚へのマッサージにも有効的らしいですよ。
3つ目の精神を安定させるです。
何か不安を感じたり危険を感じたりしたときに落ち着こうとします。
その時に見られる行為もそのひとつです。
4つ目は愛情表現です。
自分の子や飼い主に関しては愛情表現でその行為を行うと考えられています。
水を飲みやすくするため
今までは、猫の舌にあるザラザラとした突起物が水を飲むのに役立っていたと考えられていました。
しかし実際は、水を飲む時に舌先だけしか水をつけていないことがアメリカの大学マサチューセッツ工科大の研究により判明しました。
猫の舌が水面に触れて戻るときに表面張力で水が引き寄せられ、水柱ができています。
その水柱の大きさが最大になった時に口を閉じて水を口に運んでいるのです。
この動作を拘束で繰り返し行うことで水を多く飲むことができているのです。
舌のザラザラ部分には味覚はあるのか?

人間には味蕾と呼ばれる味を感じるための器官がついていますが、舌のザラザラ部分には味覚を感じる味蕾がありません。
なので、人間が感じることのできる、甘味・塩味・苦味・酸味をを感じにくいのです。
全く感じないというわけではなく、ザラザラが多いいところにある舌の中央にないのです。
しかし、酸味と苦味にはとても敏感だそうです。
中でもこの苦味は重要な役割を果たしています。
腐ったものを食べないために、アミノさんを12種類の苦味として感じ取ることができるようになっています。
食べられるのかどうか判断するために昼つようなのでしょうね。
ほかの甘味・塩味・酸味も重要な役割をもちろん果たしているので調べてみてくださいね!
猫は猫舌なの?

熱いものが苦手な人を猫舌なんて言いますけど、そもそも猫は猫舌なのでしょうか?
もちろん猫舌です。
そもそも猫に限った話ではありませんが、動物は40℃高温のものを食べる習慣はありません。
なので動物からしたら高温の食べ物は普通ではないのです。
では、なぜこんな語源が生まれたのでしょうか?
熱いものが食べられないのは猫だけじゃないので猫舌ではなく犬舌でもいいのではと思いますが、なぜ猫舌なのでしょうか?
猫は紀元前2000年代から飼われ始めたとされています。
エジプトなどの遺産物の猫を首輪をつけて飼う姿が描かれていたそうです。
日本では江戸時代にネズミ捕獲するために飼われていたそうです。
人間と一緒に生活していたため、人間に身近な存在であるといえますね。
人間と生活していくなかで当時はもちろんキャットフードなんてありませんでしたから、人間が作ったものを与えていました。
しかし、与えた食事は冷めてからしか食べない猫の姿から、猫は厚いものが苦手と広く知れ渡っていったのでしょう。
そこから猫舌という言葉が生まれたと考えられます。
チラ見している舌は何?

時々猫の口から少しだけ舌が出ているのを見かけませんか?
あれは何なのでしょうか?
これはいくつかの理由があります。
1つ目はリラックス状態
単に口に入れるのを忘れているそうです。
筋肉が緩んでいるそうです。相当安心していることが見受けられますね。
2つ目は猫主による。
ヒマラヤ・ペルシャ・チンチラなどは舌が出やすい猫主のようです。
これは顎が小さく舌をしまいにくいそうですよ。
3つ目は病気の可能性。
可能性は低いですが、まれに病気をにおわせることもあるそうです。
よだれの量が異常や口臭がすごいなど、普段にないことを感じだた病院に連れて行ってあげてくださいね。
まとめ

いかがだったでしょうか?
今回は猫の舌についてまとめてみました。
猫の舌がいかに便利だということがご理解いただけたと思います。
時々猫が飼い主である私たちをベロベロと舐めてきますよね。
あれは愛情表現なのですね!なんだかうれしいですよね。
このように猫の舌を観察すれば舌の事だけではなく猫の状態や感情も観察することができるのです!
しっかり観察していけば、何かもっとすごい発見や面白い発見ができるかもしれませんね。