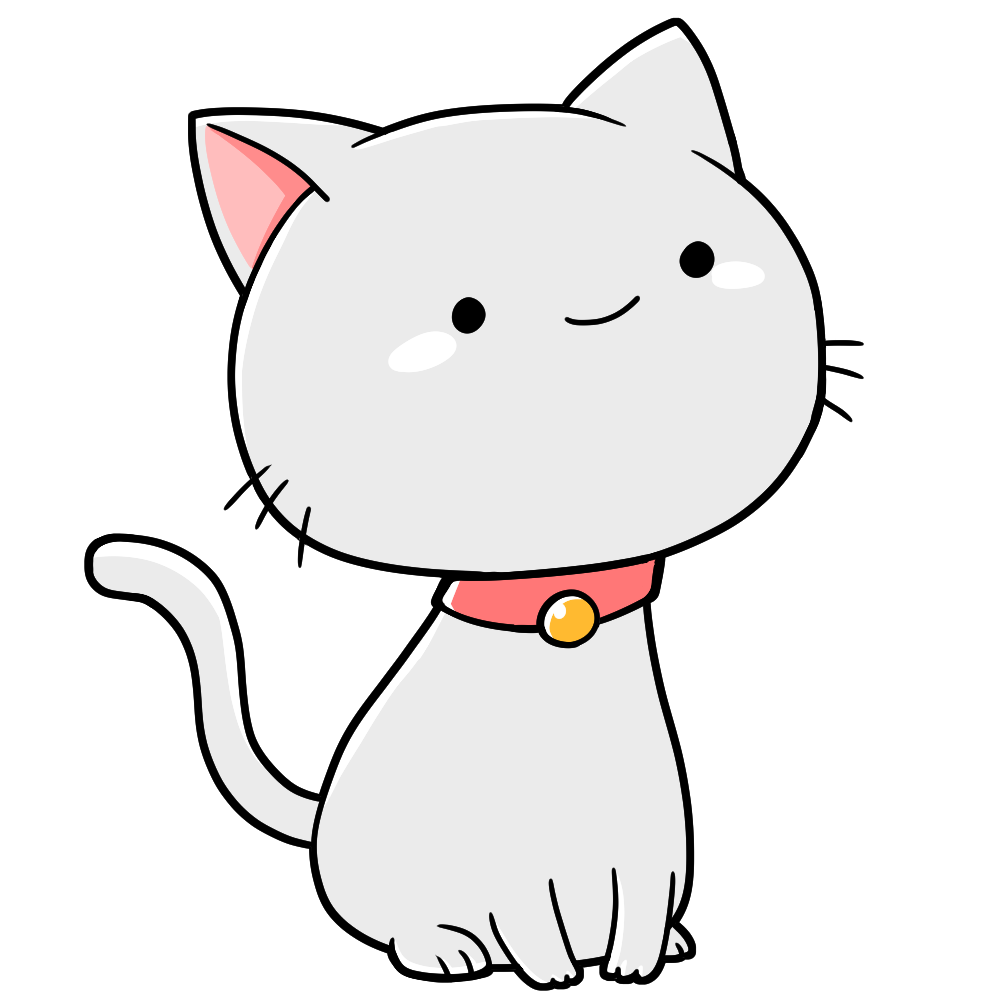猫の鳴き声はとてもかわいいですよね。
私たちが言葉でコミュニケーションをとるように、猫も鳴き声で私たちとコミュニケーションをとっているのでしょうか?
ここでは、猫が鳴く理由、鳴き声からわかる猫の気持ち、そして猫を黙らせたいときの対処法をお伝えします!
もくじ
猫が鳴く理由について
子猫は母猫に甘えるときや餌をねだるときに鳴くが、成猫になると鳴き声でコミュニケーションをとることは少なくなる。
これは、猫の祖先が狩猟や単独生活をしていたため、仲間と交わる必要がなく、鳴くことで敵に居場所を知られる危険性が高まったためと考えられている。
一方、現代のように人間と一緒に暮らすようになった猫は、「人間に気持ちを伝えるには鳴くのが一番!」と気づき、鳴くことでコミュニケーションをとることを覚えた。
かわいい鳴き声は、飼い主に気持ちを伝える手段であり、それによってさらに愛されるようになったと考えられている。
猫の鳴き声の種類について
猫は甘えたいとき、要求があるとき、不安や恐怖を感じているとき、怒っているときなど、状況に応じて声色を使い分ける。
猫がおしゃべりかどうかは品種や個体によって異なりますが、鳴き声の特徴を知ることで、猫の気持ちをある程度読み解くことができます。
それでは、猫の鳴き声を見てみよう!
親しみや甘え、要求
短い「ニャーニャー」は、親しみを感じる相手に使う。
例えば、呼びかけに対して軽く挨拶するようなものだと思ってください。
長くて甲高い「ニャーニャー」は、ペットに接したいとき、邪魔されたいとき、ペットに何かを求めるときに使う。
たとえば、ペットが食事の前に鳴くときは、『お腹が空いたよ!』と言っているのです。
ドアの近くでニャーと鳴くときは、『ドアを開けてください』という呼びかけかもしれない!
猫がドアの近くでニャーと鳴くとき、それは『ドアを開けてください』という呼びかけかもしれない!
甘えたい気持ちが強いほど、声が高く、要求が大きく、鳴き声が長くなると考えられている。
オスの方がメスよりも甘えん坊な傾向があり、オスの方がよく鳴くと考えられている。
不安や威嚇
猫が「アオーン」と低いうなり声を出すときは、警戒しているのかもしれない。
「シャー」、「フー」、「ウー」といった低いうなり声も、相手を威嚇するために使われる。
恐怖心を抱いた猫に初めて会ったとき、爪とぎなどの不快な行為をするとき、猫同士でケンカをしているときなどによく聞かれる。
このような状況で猫を困らせるのは苦痛なので、機嫌が直るまでそっとしておいてあげましょう。
発情など
発情期には特徴的な「ナーーーオ」という鳴き声がする。
鳴き声が大きく部屋中に響くため、多くの人にとってストレスになることがあります。
発情期の鳴き声は避妊・去勢手術で抑えることができるので、心配な場合は検討してみてください。
その他の特徴的な鳴き声には、「クラッキング」と呼ばれるものがあります。
これは窓の外を鳥が飛んだときに聞こえる「キャッキャッ」という鳴き声です。
これは、鳥の鳴き声を真似た歯がゆい鳴き声が獲物に届かないために発する音だと考えられている。
鳴き声の別のバリエーションとして、口を「ニャー」の形にするが声は出さない「サイレント・ニャー」がある。
猫は実際に声を出しているが、人間の耳には聞こえない周波数である。
鳴き声を静かにする対策方法
猫には猫なりの鳴く理由があるので、むやみに鳴かないようにするのは難しい。
同居人とのトラブルが心配なら、猫を飼うときに口数の少ない猫種を選ぶ価値があるかもしれない。
それでも猫がニャーニャー鳴く場合は、以下の対策を試してみてください。
他のことに気をそらせる
猫の要求に応えているはずなのに鳴き続ける場合は、何か他のもので気をそらしてみましょう。
コングのような、転がしてフードを出すことができる知育玩具を使うことをお勧めします。
コングで遊べば、ニャーニャー鳴くのを忘れるだけでなく、ペットが自分で食べ物を手に入れたという満足感も得られます!
また、自分の食べ物を手に入れたという満足感も得られるだろう。
すぐに要求に応じない
猫は飼い主と接することで日々学習しているので、「鳴けば願いが叶う」と学習しておしゃべりが増えている可能性は十分にある。
そんなときは、「鳴き止んだらリクエストに応える」という方法を試してみよう。
例えば、おやつが欲しくて鳴き続けている猫がいたら、鳴き声には反応せず、静かになったらおやつをあげる。
この方法は鳴き声の競争を伴うので難しい面もあるが、猫が学習すれば鳴き声をコントロールできるようになるかもしれない。
鳴く必要のない環境をつくる
餌を与えたり、汚れたトイレを掃除したり、一緒に遊んだりといった要求を満たさなければならない。
猫が最低限の世話を必要とする前に、あらかじめ世話をしておけば、猫は無駄な鳴き声をあげたり、あなたに振り向いたりする必要がなくなる。
猫の鳴き方から考えられる病気の可能性について
声が出ない
静かなニャーではなく、本当に発声がない場合は、病気の可能性があるので注意が必要である。
猫の発声は、喉頭を空気が通ることで行われる。
また、猫には左右に声帯があり、息を吐くときに振動して声を出します。
高齢の猫では、声帯の筋肉量が減少すると、声が小さくなり、静かなニャーという声になることがある。
また、腫瘍など、何らかの理由で発声を妨げている基礎疾患がある可能性も考慮する必要がある。
声がかすれている
何かが発声を妨げている可能性があります。
その場合は、動物病院を受診するとよいでしょう。
病気の場合の検査について
病気の場合、以下の検査が実施される。
血液検査
血液検査は主に各臓器の機能を総合的に評価するために行われ、画像検査と組み合わせて全身の状態を評価します。
症状によって、異常はある程度予測できますが、呼吸器疾患の軽症や初期段階であれば、血液検査で重大な異常が発見されることはありません。
X線検査
呼吸器系を評価するためにX線撮影を行う。
「サイレント・ニャー」の判断としてを行うこともある。
その他の検査
超音波検査、CT検査、MRI検査も行われる。
腹部と心臓を検査するので、嘔吐や咳がある場合は必ず獣医に報告すること。
まとめ
猫の鳴き声は、さまざまな感情を表現するだけではない。
猫の鳴き声がいつもと違う、いつもよりよく鳴く、いつも鳴いている猫が全く鳴かないという場合は、体調に何か問題があるのかもしれません。
鳴いている猫の行動や表情を観察して、猫があなたに何を伝えようとしているのかを確認しましょう!