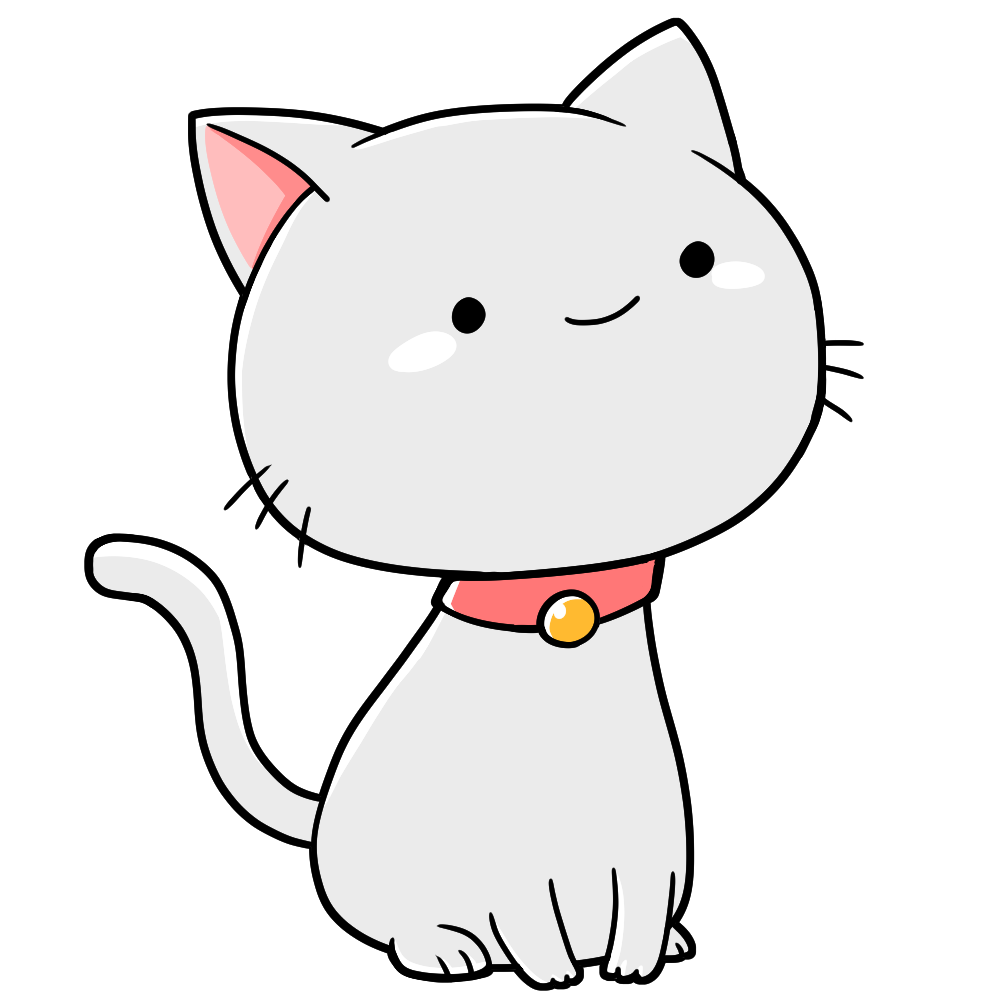猫のどこがかわいい?と質問すればほとんどの方が肉球というかもしれません。
確かにあんなにきれいな色でぷにぷにすべすべ。
かわいいとしか言いようがありませんよね。
今回はそんなかわいい肉球についてまとめていきたいと思います。
もくじ
肉球にはそれぞれ名前がある

前足と後ろ足でそれぞれ名前があるのです。
まず前足から。
指球(しきゅう)
裏にある小さな5つの肉球。
掌球(しょうきゅう)
人間でいう手のひらに存在する肉球。
指球の下にある1つの大きめな肉球のこと。
手根球(しゅこんきゅう)
前足のみにある肉球。
豆状骨(とうじょうこつ)を守るためにあると考えられています。
狼爪(ろうそう)
人間でいうと親指です。
基本的に後ろ足には存在しません。
次に後ろ足です。
足底球(そくていきゅう)
後ろ足の中心にある大きな肉球。
趾球(しきゅう)
後ろ足にのみ存在する、小さな4つの肉球。
以上が普段私たちが見ている猫はこのくらいだと考えられています。
しかし、少し特殊な猫がいます。
ポリダクティル・キャットと呼ばれる猫がいて、その猫は普通の猫よりも本数が多いいそうです。
様々な種類があり、最も多い種類で前足の指だけで左右で1本ずつ多い20本というパターンもあるそうです。
肉球の役割は?

実は肉球は猫が生活していくうえで、必要不可欠な存在でなくてはならないのです。
どんな役割があるのかそれぞれ解説していきます。
足音を消す
どの動物もそうですが、狩りをするには自分の存在を消したかのように静かに獲物に接近する必要がありますね。
肉球にはその効果があり、足音を消してくれる働きがあります。
獲物を確実に捕獲するには欠かせないものとなっているのです。
滑り止め
猫がよく、足場が悪く狭いところを通っていますよね。
なぜそういう場所でも何も問題なく移動することができるのでしょうか。
それももちろん肉球のおかげです。
肉球では、汗をかき占めることで滑り止めの効果を生み出しているそうですよ。
クッション効果
猫はいろんなところに上りたがりますよね。
降りるには飛び降りることが多いいですよね。
もちろん高いところから飛び降り着地すれば足に相当なダメージが与えられると思います。
しかし、そんなダメージを吸収してくれるのが肉球なのです。
何とも万能なのでしょう。
物をつかむ
猫は、物を掴んだり何かにしがみ付いたりします。これも肉球のおかげなのだそうです。
猫に限ったことではなく、ネコ科の動物には多く見られるそうです。
マーキング
足の指の間には臭線があるそうです。
自分の場所などに自分のにおいを付け自分のものと証明しているそうです。
肉球の正体は?

あのぷにぷにとしたかわいい感触。
あの正体は脂肪と弾性繊維(だんせいせんい)という組織なのです。
そこの部分だけ皮膚が厚くできていて、厚さは1ミリほどあるそうです。
この厚い部分は、摩耗しにくく、仮にしてしまったとしてもすぐに新しい細胞ができるようにできているのです。
しかし、ケガや事故などによって、激しい外傷を追ってしまいごっそり肉球を持っていかれると再生することができません。
肉球の色は毛の色によって決まる!?性格も?

白・グレー=薄ピンク色の肉球。
黒・茶色=チョコレート色の肉球。
肉球の構造はずっと同じというわけではなく、成長につれて模様が出てきたりすることもある。
他にも、猫の性格もわかるそうです。
肉球だけで性格が違うというわけではなく、被毛の色によっても性格が変わるともいわれています。
肉球の色は個性だととらえることができます。
肉球に触れるだけで体調をチェックできる?!

肉球は猫の平熱を確認するためにも役立っているのです。
病気になると平熱より熱くなるそうです。
熱さや濡れ具合を飼い主さんが把握しておけば、気づかない異常に気付けるかもしれませんね。
お手入れ
肉球の乾燥具合や汚れ、毛の長さなどよく見ておきましょう。
寒い季節は乾燥しやすいためカサカサになり割れてしまう可能性があるため、肉球専用のクリームも販売されているので乾燥している場合は塗ってあげましょう。
もし、汚れがある場合は濡れたタオルなどで優しくなでるように拭いてあげてください。
肉球付近の毛が長いと、高いところから着地した時に滑ってしまい怪我につながるかもしれませんので、ちょくちょく確認して、伸びていたら切ってあげてくださいね。
猫はよく自分の肉球をなめて掃除をしているため、そんなにお手入れは必要ないとされています。
もし以上のことが確認されましたらケアをしてあげてください。
猫には利き手とかある?

人間同様に「右利き」や「左利き」みたいに、どっちかの前足を多用することがあるそうです。
アメリカの大学テキサスA&M大学が調べたところ、左前足が優位的であるそうです。
このような研究結果は、調べた人によって違うそうです。
猫の肉球と犬の肉球の違いって何なの?

いろんな動物がいて肉球のある動物もたくさんいます。
日本でペットとして飼われているのは、猫と犬ですね。
その、猫の犬の肉球はどう違うのでしょうか?
見た目ではほとんどわかりませんが、構想が違うそうです。
犬の肉球
犬の肉球には「表皮乳頭(ひょうひにゅうとう)」と「動静脈吻合」という特徴的な構造があることが発見されています。
「表皮乳頭(ひょうひにゅうとう)」は表面にある凸凹としているものです。
冷たい地面に接する面積を少なくするためだと考えられています。
確かに、犬の肉球はつるつるぷにぷによりもザラザラですよね。
「動静脈吻合(どうじょうみゃくふんごう)」とは、動脈と静脈をつなげているものです。
寒い環境で生活している動物に広くみられるそうです。
その役割は、冷たい地面と接している間に、足先の血流を増加させることにより足の冷えを防いでいるのです。
体表温度が0に近づくと、拡張子血流が多くなり、足の凍傷を防ぎます。
ほかにも、低体温症になることも防いでいます。
猫の肉球
猫の肉球は外側から見て、表皮(ひょうひ)→角質細胞→真皮(しんぴー)→コラーゲンb→皮下組織(ひかそしき)→脂肪組織cとなっています。
表皮(ひょうひ」は中でも特に硬いものになっています。
猫の肉球のプニプニの秘密は、脂肪の所に先程説明した通り弾性繊維が網目状に組み込まれているため、あのプニプニとした感触が生まれるのです。
まとめ

いかがだったでしょうか?
あなたの知らない肉球の秘密を知ることができたでしょうか?
是非、猫の肉球を触ってみて理解を深めていってあげてくださいね!