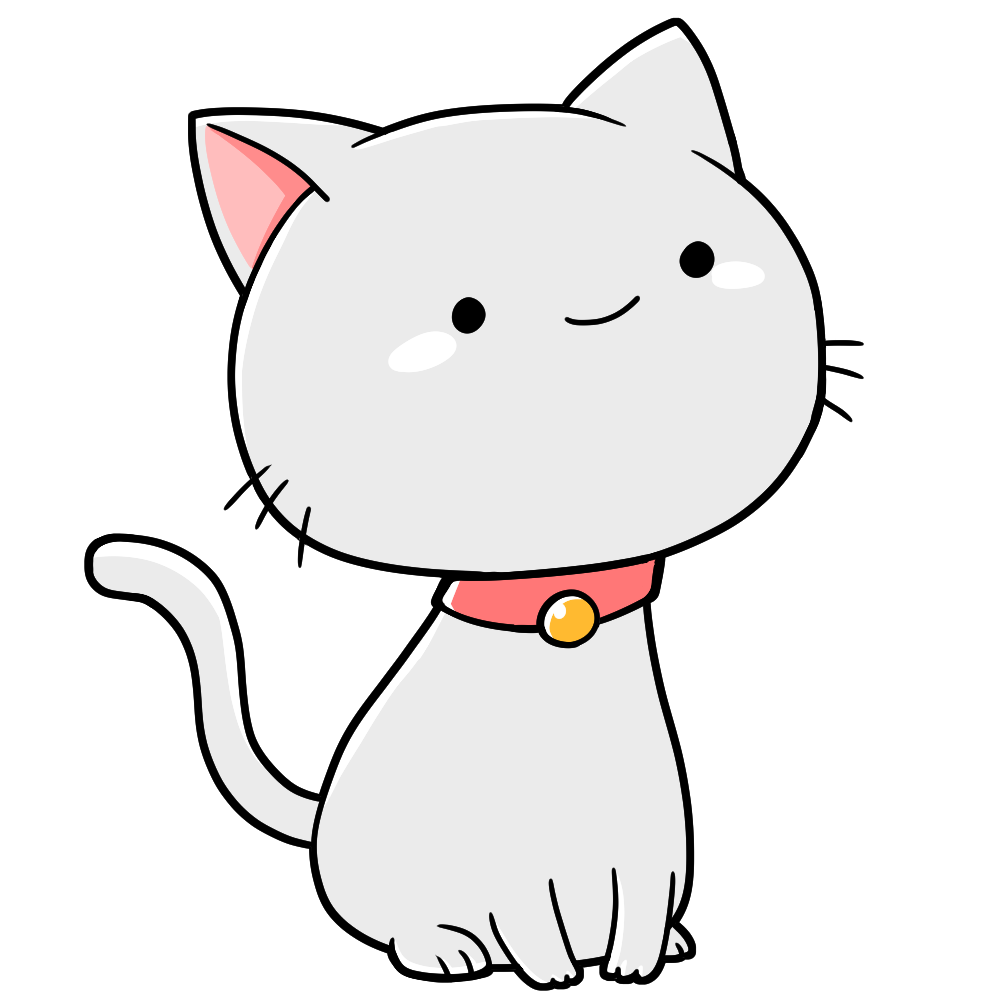毛布や枕に寄り添いながら、ふみふみする猫はとても可愛らしく、癒されるように見えます。
猫のふみふみは「安心」のサインであることが多いのですが、実はそれ以外にも理由があるのです。
この記事では、猫がふみふみする5つの理由、気をつけるべきこと、飼い主にふみふみさせる方法を紹介します。
猫の気持ちがわかると思いますので、ぜひ参考にしてください。
もくじ
猫がふみふみする5つの理由
猫がふみふみする理由は5つある。場合によっては注意が必要であることを認識することが重要である。
愛情表現・甘え
猫が飼い主にふみふみするのは、飼い主を母親として慕っている証拠だ。
猫が子猫の頃、前足で母親のふみふみして乳を出した名残である。
飼い主に触れられて気持ちよかったり、タオルケットに包まれて居心地がいいと感じたりすると、猫は母猫に寄り添ってもらったときのことを思い出し、安心するので自然とふみふみするのだ。
リラックス
猫はリラックスしているときでも、母猫と一緒にいたときの快適な状態を覚えていて、前足を勝手に動かしたりくねらせたりし始める。
この行動は、猫がお気に入りのベッドや毛布の上でくつろいでいるときに観察される。
睡眠のルーティン
いつもふみふみしてからベッドに入る猫がいる。
子猫時代に「母乳を飲んでから寝る」を繰り返したため、大人になってからも寝る前に踏み踏みしてから睡眠似入るパターンが身についた猫も多い。
ふみふみは睡眠を促すと言われている。
マーキング
ふみふみはマーキングのひとつでもある。
猫は前足に匂い線(匂いを放出する器官)を持っており、匂いでマーキングすることで縄張りを主張する。
猫が飼い主やお気に入りの物にふみふみするのは、それによって「お前は俺のものだ!これは俺のものだ!」「これは俺のものだ!」と言っているのである。
ストレス発散
ふみふみは不安やストレスを解消する必要があるために行うことがあります。
落ち着こうとしているときは、ナプキンを吸ったりかじったりといった他の行動と一緒に行うことが多い。
こんな猫のふみふみは要注意
猫はリラックスしているときにふみふみをすることが多いが、飼い主が注意すべきときもある。
以下のサインに注意してください。
これまでしなかったのに急にはじめた
今まで特にふみふみしなかった猫が急にふみふみし始めたら、興奮やストレスから落ち着こうとしている可能性が高い。
原因を取り除き、適切に対処することが大切です。
常にストレスにさらされていると、体調不良につながることもあります。
いつもと違う行動や、引っ越しや新しい猫など環境の変化など、考えられる原因を特定し、対処しましょう。
ウールサッキングと同時にふみふみする
ふみふみしながら羊毛を吸ったり、布製品を吸ったり噛んだりしている場合、その目的はストレス解消です。
ほつれた毛糸を誤って飲み込んでしまう可能性があり、非常に危険です。
ストレスの原因を探して取り除き、布製品はひとまず脇に置いておきましょう。
オス猫のうしろ足ふみふみ
オス猫がふみふみをして後ろ足を動かしていたら、発情している証拠です。
オス猫にとって、交尾したくてもできないのはとてもストレスになります。
お気に入りのおもちゃやおやつで気をそらし、交尾がエスカレートするのを防ぎましょう。
繁殖の予定がない場合は、できるだけ早く去勢手術を受けさせるのがベストです。
まれに、去勢しても発情が直らないオス猫もいますが、ストレスは軽減されるはずです。
自分が猫にふみふみしてもらうには
猫を飼う人の夢は、大好きな猫にふみふみしてもらうこと。
猫にふみふみしてもらうためには、母猫のように慕ってくれる動物との信頼関係を築く必要がある。
以下のヒントを参考にすれば、猫になつかれない可能性が高まります。
猫には「リラックスしているときにふみふみするする」という性質があることを認識し、日頃から愛情を注いでリラックスした生活を送れる環境を作ってあげることが大切です。
構いすぎるとストレスになる猫も多いので、猫がどちらの拭き方を好むか、どの程度距離を置くか、一人の時間を作ってあげることも大切です。
ふみふみしない猫もいるので無理はしない
そもそも、ふみふみはネコの子供時代の遺物であり、だからこそ、親からきちんと引き離された成猫の多くはしないのである。
気質的にふみふみをやらない猫もいる。
ふみふみをやってほしいとは思うが、飼い主の理想を押し付けすぎるとストレスになる。
無理強いはせず、猫が気持ちよく過ごせるように接しましょう。
まとめ
猫がふみふみする理由は、愛情、リラックス、睡眠パターン、ストレス解消、マーキングの5つ。
突然習慣化したふみふみは、ストレスや不安を解消するための行動の可能性があり、注意が必要です。
原因を突き止め、必ず取り除くこと。
飼い主が母猫として猫の信頼を得れば、無駄吠えにふける可能性は高くなりますが、親離れ度合いや性格の違いからふみふみをしない猫もいます。
ストレスを与えないためにも、無理強いしないことも大切だ。