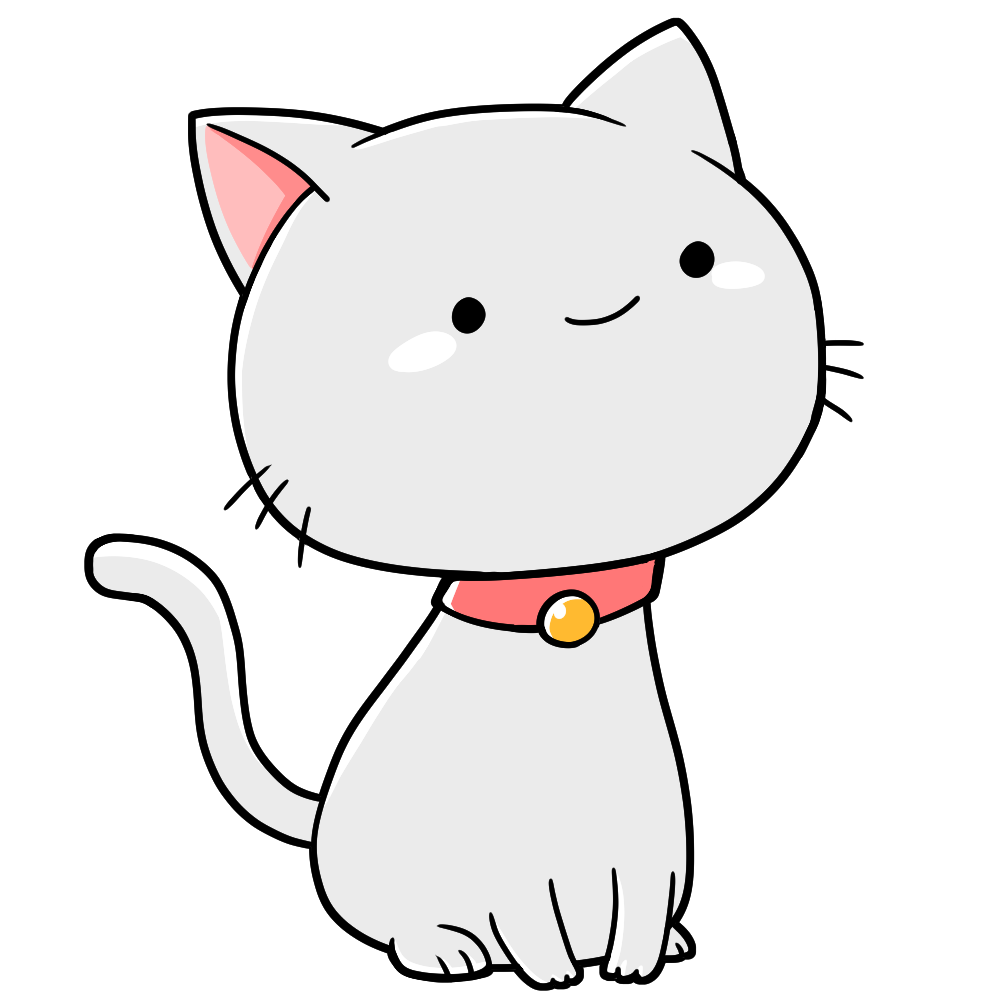ありのままで、愛しい我が子。
甘えてくる?猫の魅力のひとつは、その自由奔放な行動だ。
猫の複雑な思考や感情をすべて知ることができたら……?
それは飼い主に大きな喜びを与えるだろう!
今回は、しっぽや鳴き声、仕草や行動から猫の気持ちを知る4つの方法をお伝えします。
もくじ
しっぽでわかる猫の気持ち
尻尾は、「尾椎(しっぽ)」という小さな骨が連なってできており、しなやかで多様な動きを可能にしています。
その役割は、身体のバランスを取ることはもちろん、猫同士のコミュニケーションにも役立っているのです。
飼い主さんもこの表現豊かな猫の尻尾から、感情を読み取るチャレンジをしてみませんか?
しっぽが垂直に立っている時
猫のしっぽがピンと立っているのは、幸せいっぱいの合図。
帰宅したときに猫がこの状態で出迎えてくれたら、「おかえり! 早く遊んでよ!」ということです。これは「おかえり」とも解釈できる!
このしぐさは本来、子猫が母猫に近づくときに自分の存在を示すために使うものだが、成猫が母猫に敵意や友好的な感情がないことを示すために使うと考えられている。
子猫が飼い主の方を向くのは、甘えている証拠。
撫でてあげたり、遊んであげたりすれば、きっと喜ぶだろう!
しっぽを足の間に巻き込んでいる時
猫が後ろ足の間で尻尾を丸めているのは、「怖い」と感じている証拠だ。
カメのように体を小さくすることで、防御の姿勢をとっていると考えられます。
お迎えして間もなくこのような仕草をするようになった場合は、環境の変化が原因かもしれません。
特に、何を怖がっているのかに注意してください。
例えば、掃除機や洗濯機の大きな音は、猫にとって「未知の恐怖」です。
余計なストレスを与えずに過ごせるよう、そのようなものには近づけないように気を配ってあげましょう。
しっぽを速く動かす時
「ブンブン!」という音が聞こえてきそうなくらい猫が尻尾を速く動かしている時は、機嫌がよくなかったり、何か「戦う相手」を見つけてしまったところかもしれません。
こういうときは無理に触ったり抱っこしたりせず、そっとしておくことが得策です。
そう、犬では喜びの合図として知られていますが、猫では逆なのです。興味深いですね。
しっぽを小さく速く動かす時
猫の感情が特に複雑なのは、尻尾が「ぴくぴく」と小さく速く動くときだ。
状況にもよるが、これは猫が何かを考えていることを意味したり、不安や緊張を感じていることを意味したりする。
少なくとも、しっぽを「速く振る」ときほどリラックスしているわけではないので、無理強いせず、落ち着くまで自由にしておくのが一番です。
猫の鳴き声でわかる猫の気持ち
猫の鳴き声といえば、「ニャー」とか「ニャア」といった言葉が思い浮かぶが、一緒に暮らしてみると、鳴き声の種類(イントネーション、長さ、音の高さ)が違うことに気づく。
この「ニャー」から猫の気持ちを読み取ってみよう。
ゴロゴロと喉を鳴らす時
喉の奥から出る「ゴロゴロ、ゴロゴロ」は鳴き声とは言えないかもしれないが、これも重要なシグナルである。
一般的には、猫がリラックスしている、あるいは甘えているサインだと考えられている。
猫がなぜ鳴くのかについてはいくつかの説があるが、この音は子猫が母猫にミルクをきちんと飲んでいることを知らせるために出すという説もある。
子猫を撫でたときにこの音が聞こえたら、飼い主の腕の中に入れられてホッとしていることがわかる。とても満足感がある。
ニャー、ニャオと鳴く時
小さな子供が猫を「ニャーニャーニャー」と呼ぶのは、この鳴き声のためである。
これはいわゆる “猫の鳴き声 “である。
これは一種の挨拶であり、何らかの行動の前兆である。
ウー、シャーと鳴く時
牙を剥き出しにして「シャー!」と悲鳴をあげているのを見たら、間違いなく機嫌が悪いのがわかる。
この音は怒っているときや不安なときに出ます。
猫は興奮状態にあるので、なだめるのではなく、落ち着くまで観察してください。
例えば、新しい猫を飼っていてこの声が聞こえたら、先住猫とケンカしないように注意深く観察してください。
仕草から分かる猫の気持ち
私たちにとってはかわいい仕草だが、そこにはネコの感情が込められている。
もしそうであれば、彼らからも感情を読み解いてみてはいかがだろうか。
代表的な例をいくつか挙げてみよう。
耳を横に寝かせている時
猫の聴覚は非常に優れている。
人間には聞こえない音(高周波)を拾うことができると言われている。
この耳が平らになっているとき、猫は最もリラックスした状態にある。
心地よさを感じたり、リラックスしたりすると、耳はリラックスし、チクチクするのと同じような状態になる。
リラックスした状態の猫を見ていると、自分もリラックスした気分になれるかもしれない。
威嚇する時
毛が後ろに投げ出され、背中が丸みを帯びているので「一回り大きく」見え、威嚇したいという気持ちが表れている。
この時、尻尾がタヌキのようにフワフワしているのも特徴だ。
鳴く犬と同様、そっとしておくのが一番だ。
体を小さくする時
前述とは逆に、動物が臆病になったり、体をできるだけ小さくしたり、丸まったりする場合は、恐怖のサインと考えるのが正しい。
また、緊張している(固まって動かなくなる…)こともある。
怖がっているものを遠ざけたり、見えなくしたりして、安心させてあげるとよい。
片足を上げて止まる時
猫が前足の片方を手招きするように上げて固まっているのを見たことがあるとしたら、それは「逃げるか、殴るか……!」という状態で、次にどうしたらいいのかわからないということだ。
このような状況に陥った場合、おそらく手に汗を握っていることだろう。
猫の行動から分かる猫の気持ち
見ているだけでも安心しますが、その行動の意図を理解すれば、猫の「今の気持ち」をより深く理解することができます。
ここでは、代表的な行動を挙げてみたいと思います。
すりすり寄ってくる時
猫が擦り寄ってきた瞬間、飼い主は「甘えているのかな」と目を細めてしまうだろう。
もちろん、それはそれで当然なのだが、同時に猫の臭いを刻み込む行為でもある。
こすりつけとも呼ばれるこの行動は、マーキングの一種です。
マーキングの一種であり、飼い主についた他の匂いを一生懸命消そうとしているような、愛情表現でもあるのだ。
なめてくる時
猫があなたを舐めるとき、少しざらざらした感触があることに気づくだろう。
舌をよく見ると、とがった突起が見える。
これは猫の舌の特徴で、水を飲んだり毛づくろいをしたりするのに役立っている。
このように、舌は猫の生活においてとても重要な器官なのです。
もし猫がそのような舌で舐めたとしても、ネガティブな感情を抱いていると考えるべきではない。
それどころか、まるで家族や友人に向かって、”今、毛づくろいをしているよ “と言っているように感じるはずだ。
愛情表現として受け止め、優しく接してあげましょう。
集団で行動する時
猫は単独で行動する動物というイメージが強いが、野良猫の集まりなどでは集団で行動することもある。
自宅で複数の猫を飼っている場合(いわゆる多頭飼い)、必然的に群れで行動することになるが、その場合でも微妙な距離感が保たれているのが普通だ。
パワーバランスにもよるが、例えば特定の子が日当たりの良い場所にいるか、風通しの良い場所にいるかなどを注意深く観察する必要がある。
毛づくろいをする時
グルーミングは猫にとってとても重要な習慣だ。
汚れを落とすことで体を清潔に保つためだ。
しかし、不安を感じたときにリラックスするために毛づくろいをすることもある。
リラックスしているから毛づくろいをすることもある。
猫たちが今、グルーミングをどのように感じているのか、ぜひご覧ください。
まとめ
猫を大切な家族の一員として受け入れたら、今までは「かわいい」だけだった猫の行動やしぐさのひとつひとつから、猫の気持ちを読み取りたくなるのではないだろうか。
ここに挙げたのは典型的な例だが、猫にも個性がある。シチュエーションによって見せる感情も違う。
猫の気持ちを理解し、温かく見守ることで、深い絆で結ばれることを願っている!