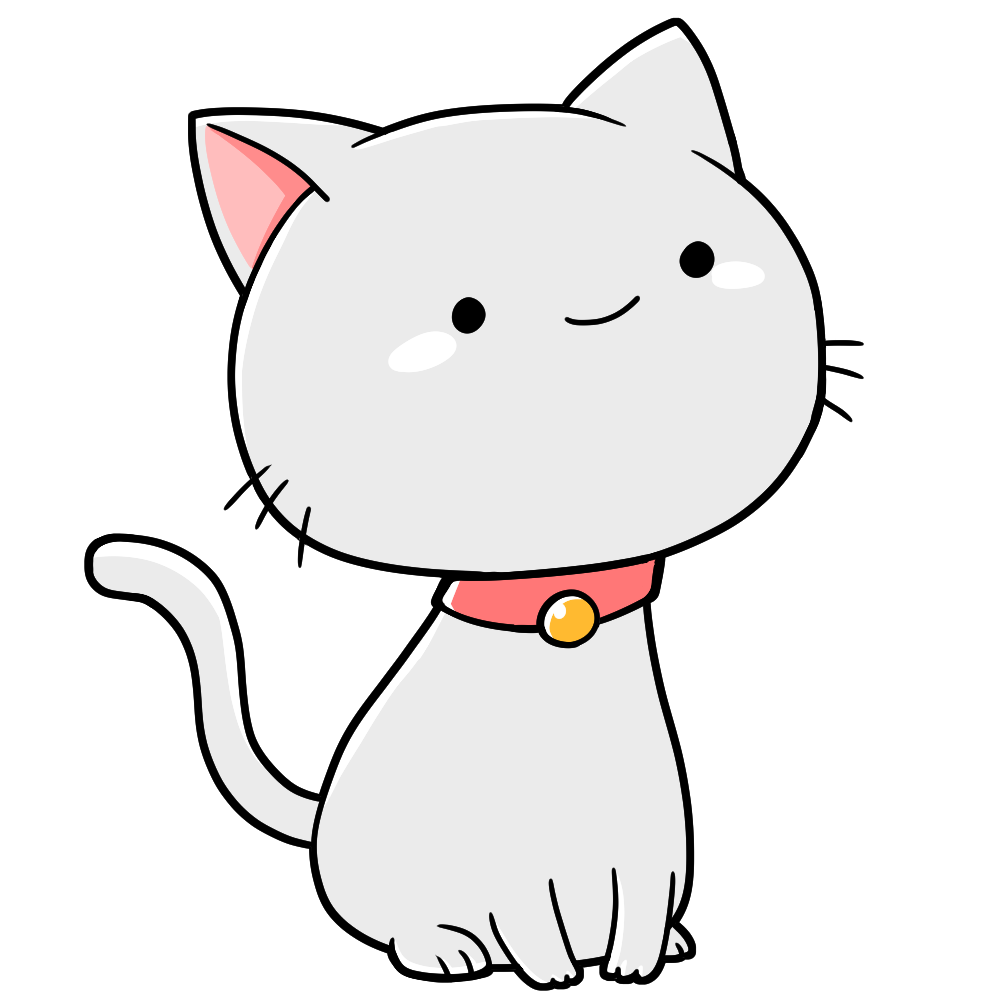猫が肩などに飛び乗ってきて、爪が体に食い込んで痛い思いをしたことがある人もいるでしょう。
爪切りは、愛猫をケガから守るだけでなく、感染症を防ぐためにも大切です。
猫の爪切りが難しすぎるという方のために、成功するためのコツをご紹介します。
もくじ
猫の爪切りの必要性について
猫に爪切りは必要か?
爪切りと猫用爪切りは、その用途が大きく異なる。
猫の爪は球根状の層構造になっており、爪切りをする際には、古い外側の爪を剥がして新しい爪を露出させる。
爪切りでは爪の先端は削り取られないので、切りそろえる必要がある。
病気やケガのリスクについて
猫は家の中で暮らしていると、狩りをしたり木に登ったりする必要がないため、爪を切っていないとどんどん伸びてしまう。
伸びた爪が家具やカーテンに引っかかったり、猫のパッドに詰まったりする危険性もある。
また、感染症の猫にひっかかれると、猫ひっかき病やパスツレラ症などの感染症にかかることがあります。
猫ひっかき病は、ひっかき傷の部位の発赤やリンパ節の腫れ、発熱、頭痛、倦怠感などの症状を引き起こします。
パスツレラ症は肺炎を引き起こすことがあり、免疫不全の個体や糖尿病などの持病のある個体では、重症化して死に至ることもある。
どちらの感染症も猫にはほとんど症状が出ないので、「うちの猫は健康だから」と油断しないようにしましょう。
爪切りを行う頻度について
子猫(~1歳まで)
目安は2週間に1回
爪の手入れがまだうまくできず、引っかかりやすいので、こまめな爪切りをおすすめします。
成猫(1歳~7歳まで)
月に1回の使用をお勧めします。
高齢猫(7歳以上)
目安は2週間に1回。
爪切りの回数が減り、爪自体が太くなってきます。
太い爪が伸び続けると肉球を傷つけることがあるので、定期的に爪の状態をチェックする。
爪切りに必要な道具について
猫の爪とぎにはいろいろな種類があるが、ハサミ型とギロチン型を覚えておくとよい。
ハサミは、私たちが普段使っているハサミに近い感覚で使えるので初心者には便利で、厚くなった爪や巻き爪を切るのにおすすめです。
ギロチンはハサミよりも力が伝わりやすく、硬い爪を切るのにおすすめ。
爪切りの切れ味が悪いと時間がかかり、猫に不快感を与えるので、定期的な交換を忘れずに。
爪切りを嫌がる猫の場合は、リネンネットや大きめのバスタオルを体に巻いてあげると、動きをコントロールしやすくなる。
また、爪を切りすぎると出血することがあるので、ガーゼやコットン、消毒薬を用意しておくとよい。
猫の爪切りを行う流れについて
多くの猫は足先を触られるのをとても嫌がります。
猫と接するときは、定期的に足の指を触る練習をしよう。
猫が触らせてくれるくらいおとなしくなったら、爪を切ってみましょう!
最初に
猫が落ち着ける姿勢を見つける。
膝の上に乗せたり、横向きに寝かせたり、リネンネットやバスタオルでくるんだりしてみましょう。
手伝ってくれる人がいれば、その人に猫を抱き上げてもらい、ペースト状のおやつを舐めさせて気をそらす。
次に
ポーズが決まったら、爪切りを始める。
前足を触られるのを嫌がる猫も多いので、まずは後ろ足から。
前足を軽く押して爪を離し、ピンク色に透けて見える血管を確認する。
ポイントは、爪の先端を血管の先端から2~3mm以上へこませて切ること。
誤って血管の先端に余裕を持たせずに先端を切ってしまうと、猫に痛みを与えてしまう。
ひとたび痛みが生じると、爪切りは恐怖の体験となるので注意が必要だ。
最後に
爪切り後は、おやつを与えたり、お気に入りのおもちゃで遊んであげたり、猫が喜ぶことをしてあげましょう。
猫に爪切りは良いことだとポジティブな印象を与えることで、爪切りを繰り返す可能性が高くなる。
特別なおやつを用意するのもいいアイデアだ。
猫の爪切り成功のコツについて
爪切りをまったく怖がらない猫もいれば、爪先を触らせることすらできない猫もいる。
最初は1日1本ずつ、徐々に爪切りに慣らしていく。
大切なのは、猫が嫌がったらすぐにやめることと、爪切りのタイミングを見計らうことだ。
爪切りをしている最中に尻尾を振り始めたら、機嫌が悪くなっている証拠なのでやめること。
爪切りは、犬がリラックスしているか、寝起きで少しぼーっとしているときにするのがコツだ。
猫の爪切りをする際に注意すること
爪切り中に出血した場合は、ガーゼやコットンで圧迫して止血する。
止血剤で圧迫すると早く止血できる場合があります。
爪の血管は細く見えますが、出血すると止まりにくいので、圧迫しても出血が止まらない場合は獣医に連絡してください。
まとめ
いかがでしたか?
爪切りをしたことがない方は、ぜひこの記事を参考に練習してみてください。
アドバイス通りにやってもうまくいかないこともあるので、あきらめずに練習してみてください。
もし猫が嫌がるようなら、無理強いせず動物病院に相談することをおすすめします。