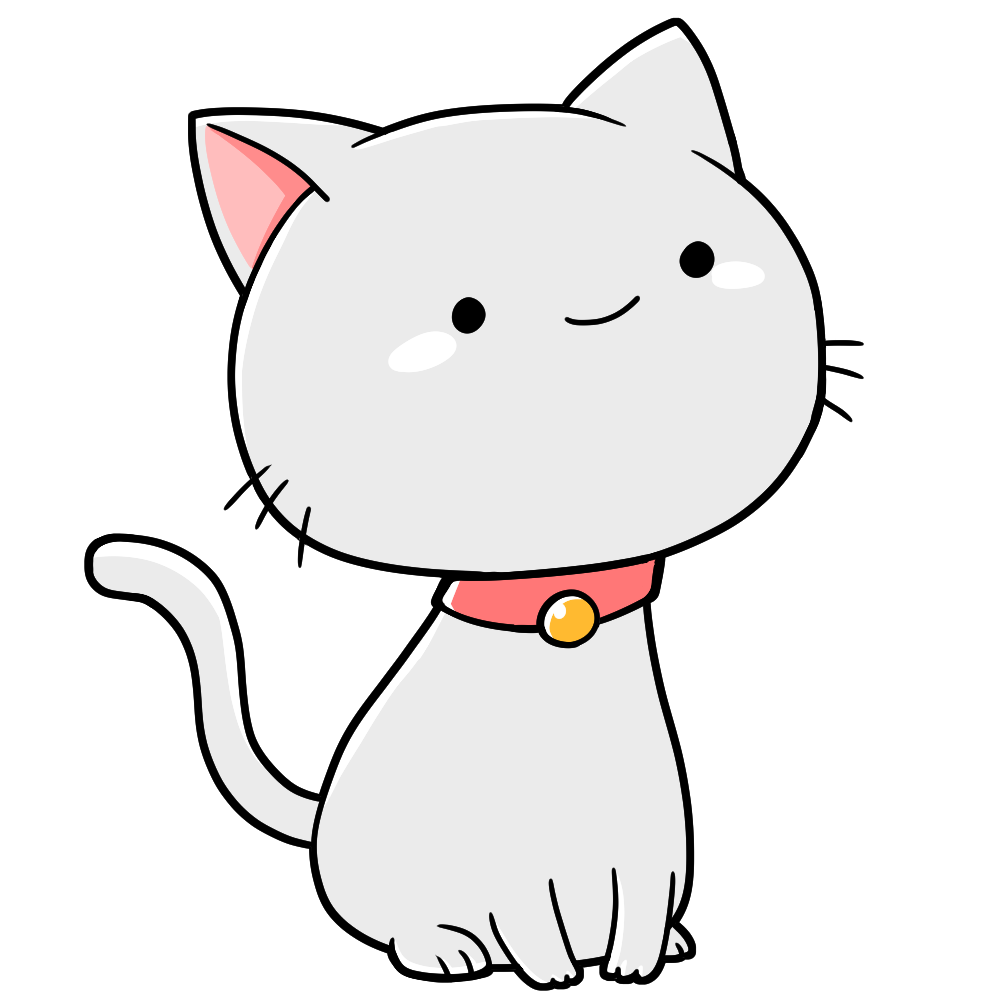猫は年齢や体質などでかかりやすい病気は変わってくるのです。
なので、今回は成猫を中心に詳しく病気の事。
そしてそれを防ぐための薬やワクチンについて詳しく解説していきたいと思います。
もくじ
かかりやすい病気は?

先ほど言ったように体質などによってかかりやすい病気は変わってきます。
なので、今回は平均してかかりやすい病気をまとめてみました。
まず一つ目は、泌尿器系です
泌尿器系で多いいのは、膀胱が炎症を起こしてしまう「膀胱炎」や、入道に石が詰まってしまう「尿石症」です。
まとめると、病名「下部泌尿器症候群(尿石症、膀胱炎、尿道閉塞)」
主な症状としては「おしっこが出ない・頻尿・血尿」
尿道閉鎖は尿石症でできた結晶が尿道を塞いでしまいおしっこが全くでない状態です。
人間でもこのような病気があります。
それは「尿路結石」です。
猫も人間同様で激痛を伴うため、早めに気づいてあげることがいいでしょう。
もしかかってしまったら「飲み物の飲む量を増やし、ウェットフードを取り入れる」
防ぐ方法としては、「マグネシウムを多く含む水は控える」などがあります。
二つ目は糖尿病です。
症状は「多飲、多尿、初期は多食、後期は食欲不振」
インスリンによって等を取り込む働きが正常に作用しなくなり、体内にうまく取り込めず尿として排出してしまうことです。
これは、肝不全や肝不全などの合併症を起こしてしまう可能性すら出てきます。
対策としては、カロリー調整や運動管理を行う。肥満を予防する。
三つ目は、慢性腎不全です。
症状「嘔吐、食欲不振、やせる、多飲や多尿」
血液の中の老廃物をろ過し、尿を取り出す肝臓の組織が壊れて今うことで、ほとんど機能しなくなってしまうこと。
対策はない。なぜなら壊れたものはもう再生することができないからです。一番の策としては進行を遅らせることだけだそうです。
四つ目は、カゼです。
症状は人間と似ている部分も多く例えば「くしゃみ、鼻水・体が熱くないか?」など。
環境の変化た免疫力が下がってしまった時などに多いそうです。
寒暖差が激しい季節の変わり目などには注意しましょう!
最悪死に至ってしまう病気はあるの?

やはり感染症は命に係わる危険な病気が多いいそうです。
その病名は「猫伝染性腹膜炎」です。
猫伝染性腹膜炎とは、「猫コロナウィルス」に伝染した後に体内で毒性の強い「FIPウィルス」に突然変異することにより発症します。
ほかの猫からウィルスが体内に移ると考えられています。
今のところワクチンがなく、発症してしまうと死に至る可能性が大きいそうです。
症状は、高熱が出ることはほとんどなく、多くの場合目の虹彩が赤く濁ることで発覚することがあるそうです。
予防方法は、トイレや猫が飲むための水は清潔や新鮮なものを与えたりすることが一番の予防策とされています。
感染症から守るワクチンは?種類と費用はどのくらい?
 感染症を防ぐには定期的なワクチンの接種が一番有効とされています。
感染症を防ぐには定期的なワクチンの接種が一番有効とされています。
家の中だから大丈夫だと思う飼い主さんも多くいると思いますが、実はそんなことは関係なくどんな状況にいても感染症にかかる可能性は大きくあるのです。
どこで感染する?
多くの場合、ウィルスを持った猫の唾液などの体液、排泄物に触れることによって伝染します。
室内だから大丈夫と思っている飼い主さんもいますが、確かに外にいる猫よりウィルスに触れる機会は少ないですが、全くかからないというわけではありませんので注意してくださいね。
室内で飼っている猫はどのように感染するのでしょうか?
①母子感染
お母さんが感染していた場合、母乳を返して感染する場合があります。
②空気感染
ウィルスを含んだものが、風に乗り室内などに入り込むことがあります。
③飼い主からの感染
人間の病気が猫に移ることはありません。
しかし、飼い主の服に感染症を持った猫の体液などがついていて、それが乾燥し飼い猫に移ってしまうか、猫がそれをなめるなどをして感染する場合もあります。
ワクチンで予防できるのか?
調べた結果数種類ほどありました。
| 病名 | 治療方法 | 治療費 |
| 猫ウィルス性鼻気管炎 | 診断を行った後に注射 | 6,000円 |
| 猫カリシウィルス感染症 | 診断後に注射、内服薬や目薬による治療 | 7,300円 |
| 猫クラミジア感染症 | 診断後に注射、内服薬や外用薬 | 6,630円 |
| 猫白血病ウィルス感染症 | 検査後に注射、内服薬で治療 | 39,350円 |
| 猫免疫不全ウィルス感染症 | 不明 | 不明 |
かかってしまった時の対処法は?

猫はもともと痛みに強い動物なのだそうです。
なので、痛みを我慢していることがあるため、気づいたら病気にかかっていたなんてことはまれじゃないのです。
ここでは、病気の疑いがある場合とかかっている時の場合の両方を中心に対処方についてご紹介します。
病院へ行く
まずこれが確実です。
飼い主が一緒に行ってあげることによって猫も安心して診察を受けることができますよ。
検査を行い原因を突き止める
症状の種類によって検査方法が変わる場合もあります。
検査を受ける場合は猫が服用している薬などを持参しましょう。
治療方法を探す
検査結果により治療方法は変わります。
しっかりとお医者さんと相談しましょう。
保険に加入しているかしていないかで料金も変わりますので、事前に保険に入ることをオススメします。
手術などがある場合
一番問題となるのが日程です。
かなり大きな病気で入院などをしている場合は日程などは調整する必要はありませんが、自宅療養の場合は都合が合わない日があると思いますので、事前に日程を調節する必要があります。
飼い主がするべき配慮
猫は人間と違い自分の食生活を見直すことはできません。
なので飼い主である人間が見直してあげる必要があります。
他にも、脱水症状は病気の治療に悪い影響を与えてしまうため、猫には多くの水を飲んでもらいましょう。
薬については、飲ませることが難しいため工夫が必要です。大半の動物は薬単体では飲んでくれません。
なので朝混ざるのもありですが残してしまう場合もありますので注意してください。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回紹介した対処法については一番大切となるのが飼い主の気持ちです。
飼い主のあなたが落ち込んでしまうと猫も雰囲気を吸い取りストレスを溜めてしまうことがあるそうです。
なので、飼い主のあなたは「絶対治す!」というか強い気持ちで一緒に病気と闘ってあげましょう!
一番はかからないことですよ!